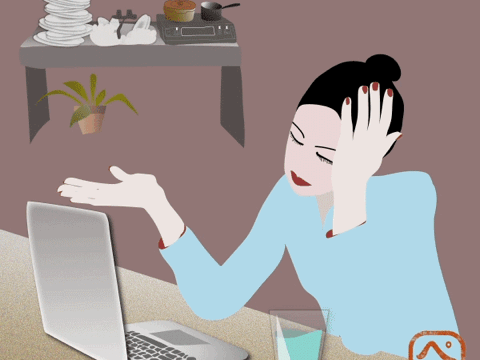わたしたちの家を見て、いすみの地元の人は率直に言う。
「こんな家、よく、買いましたね」
「こういう家に住みたいって感覚、ちょっとぼくらにはわかんない」
古民家を好きなのは都会人だけ。それはまるで田舎の人の好みではないのだ。
田舎の人はツルツル、ピカピカしたモノが好き。それに対して、都会の人はザラザラ、ゴワゴワしたモノが好きだ。
考えてみれば、白洲正子も、ソローも、ターシャ・チューダーも、古いモノや自然を愛した著名人は誰もが、もともとは生粋の都会人だった。古いモノへの愛着や郷愁は、古い建物が次々と壊され、イエの絆がうすくなり、世代ごとに職業や価値観やライフスタイルが刻々と変わってきた環境でしか生まれないのかもしれない。そんな場所に生まれ育ち、はるばる古民家求めてやって来たわたしたちは、江戸時代と地続きのいすみの人にとってまるで異星人なのだ。
「でも、わたしたちからしたら、この村で本当に素敵な家は古民家だけですよ…
それほど率直でない新参者のわたしは心の中でつぶやく。
そう。江戸時代から続くいすみの田園や寺社、ひなびたローカル鉄道の景色はたしかに美しいが、家は微妙だ。立派といわれる家はわたしたちの目にはあまり美しく映らない。お決まりのように庭がコンクリートで固められ、樹木は窮屈な標準形に刈り込まれた家。縁側の開口部は規格品のアルミサッシ窓に安手の化繊のレースカーテンがぶらりぶらりと垂れ下がっている。どの家も、畳の上に絨毯が敷かれた日本間に、ピアノやら、ぶら下がり健康器やら、骨董やら日本人形やら、埃をかぶったそれらのモノが、まるで地層のように折り重なっているのだ。そして、そんな母屋の横に建つのは、若い世代の輸入ログハウスやメルヘン調の出窓付きの家。ロココ風唐草模様のアルミサッシの門やレンガを敷き詰めたイングリッシュガーデン、キッチュなギリシャ風彫刻の白い庭石。それらが田んぼや樹木に隠れてそれほど目立たないのがせめてもの幸いである。
わたしたちが今の家が気に入ったのは、それが、珍しくそういう昭和の履歴を全部スキップして戦前にタイムワープしたような古民家だったからだ。だが、おそらく、地元の人にしてみれば、それこそが、封建的暗黒性、モノの乏しさ、息詰まる人間関係、不衛生、不合理性の象徴なのだった。

◁都会の人の郷愁を誘う古民家のシンプルな寄棟屋根は、地元の人にとっては暗い時代の象徴なのかも
いすみの人にとってさらに不可解なのは、わたしたちがその家の後進性を一向に改善しようとしないことだろう。夫はいつの間にか、わたしをはるかに上回る古民家原理主義者になっていた。「アズ・イズが一番」と宣言し、暮らしの快適さを目指したリノベーションをする気がない。理想は日本民家園に保存されているような家。わたしたちは、アルミサッシの窓は全部取り払い、昔ながらの木枠の窓に変えてしまったし、照明は蛍光灯から白熱灯に戻した。庭には、コンクリートを打たず、除草シートを敷かず、除草剤も使わない。整地をせず、エンジン式の刈払機もあまり使わず、2週間に一度、鎌で低木と雑草を刈って、ホームセンターで買ってきた植木をまるでおままごとのようにちまちま植えるだけ。

△千葉県芝山公園にある旧藪家住宅。理想のスタイルは、こんな清潔で清楚な日本古来の佇まい
それにしても、ザラザラ好きな都会人とツルツル好きな田舎人のちがいは一体、どこで生まれたのだろう?
考えてみれば、わたしのように高度成長時代以降の東京に生まれ育った人間にとって、「清潔で安全で快適な環境」は子供時代から当たり前にずっとあるものだった。だからこそ逆説的に、経済成長の恩恵よりむしろ弊害ばかりに意識が注がれてきた気がする。「便利すぎる生活は悪いことです」「科学技術の発展と人間性を調和させなければなりません」──ますます生活がツルツル、ピカピカと快適になる70年代。わたしが通ったサラリーマンの子弟が通う新興住宅地の新設マンモス小学校では、子供たちにはそんな「反文明」的な作文を書くよう指導されていた記憶がある。
だが、おそらく、農村はその真逆だったのだ。農業を営んでいれば、どれほどの技術的進歩や生産性の向上はあっても、基本的に自然や土との接触や過去とのつながりが切れることはない。変化や進歩はゆっくりで、反文明の精神が生まれるほどモノが過剰になることはない。発展も不十分ななか、若者が少なくなり、縮小再生産を繰り返しながらゆっくり衰退していく今、残された人は、せめて「清潔で安全で快適な暮らし」をしたいと望み続ける。もっとプラスチックとコンクリートのある生活。それが、21世紀のいまも、農村に生まれ、住み続ける人たちの切ない思いなのだ。
同質的な国民性と言われるものの、実際にはこのように希求する理想とベクトルがまるで異なる人たちが共存しているのが日本なのだった。
農村の人たちの思いは、実際にいすみの古民家と都会のマンションを行ったり来たりする生活でだんだんわかってきた。高温多湿の風土で広い庭を管理するのは実に大変な労力が要ること。土に囲まれた古い家は、家は温度、湿度の管理はもとより、清潔を維持するだけで大変だということ。21世紀のわたしたちは、もはや江戸時代の衛生や快適度ではすっかり満足できなくなっている。のみならず、人々の平均寿命は2倍に伸び、農村に住む人の多くが昔ならとっくに死んでいたような年齢だ。人手のない家やお年寄りにとって、庭をコンクリートで固め、家は埃が入らないようアルミサッシで密閉するのが、結局のところ、一番、衛生的で快適な暮らし方なのだった。
「田舎の人は新しモノ好きで、古いモノを大切にしない…」というようなわたしたちの批判精神は徐々に打ち砕かれていった。伝統は何も古民家のようなモノだけに宿るわけではない。いや、むしろ、目に見えないところにこそ宿る。
たとえば、いすみの地元の人が行くレストランには椅子がない。誰もが靴を脱いで、床に直に座って食事をする。地元の子供たちは、大人同様、食べ終わるまで決して見事な正座の姿勢を崩さない。その姿はわたしたちにはまるで無形文化財のように映る。端然と正座し、学校の登下校時には家の裏にある先祖の墓で手を合わせる子供たち。それに引き換え、夫もわたしも、もはや5分以上正座ができない。お盆にお墓まいりしたこともなく、3代前の先祖の墓がどこにあるかも知らない。お盆の風習を知らず、神棚や仏壇の手入れの仕方を知らず、共同体の祭りも知らない。
やさしいいすみの人たちは、そんな自分たちと異なる存在を決して裁かない。首を傾げても、裁かない。立ち入らず、裁かず、それでいて、不器用で頭でっかちな、まるで外国人のような根無し草のわたしたちをやさしく気遣ってくれる。
そう、ピカピカツルツルとザラザラゴワゴワはメビウスの輪のようにつながっている。いすみと縁を持つことで、もしかしたら、わたしたちも少しだけ、やさしく、謙虚な人間になったかもしれない。